|
HANDEL 1724 |
HWV18
オペラ イタリア語
初演:1724年10月31日、ヘイマーケット国王劇場
台本作家:フランチェスコ・ニコラ・ハイム
原作:フランチェスコ・ガスパリーニのオペラ《タメルラーノ》(ヴェネツィア、1711)へのアゴスティーノ・ピオヴェーネの台本
イッポリート・ザネッラによるその改訂台本《バヤゼート》(レッジョ・エミーリア、1719、音楽はガスパリーニ)
秀作ぞろいのヘンデルの第1次アカデミー時代の作品の中でも、この《タメルラーノ》は異彩を放っている傑作です。
《ジューリオ・チェーザレ》の成功の後、ヘンデルは夏になって次のシーズン向けのオペラの作曲に取りかかります。これが《タメルラーノ》です。
アゴスティーノ・ピオヴェーネの台本をニコラ・ハイムが手直しして台本を作り上げると、ヘンデルはいつも通りの速さで書き上げます。7月3日に作曲を開始し、その月の23日にはもう全曲を完成させています。
その後ソプラノを想定していたイレーネ役がコントラルトのアンナ・ドッティに変更になったため修正を加えた程度で、ヘンデルは作品を完成させたつもりでいました。
ところが、この後ヘンデルは一度完成させた《タメルラーノ》を大幅に書き直しています。その理由は、新しい台本と出会ったことでした。
バヤゼート役を歌うことになっていたテノールのフランチェスコ・ボロジーニが9月の始めにロンドンに到着した時、彼は自分が主演したガスパリーニのオペラ《バヤゼート》(1719年、レッジョ・エミーリアで上演)の台本を持って来ていたのです。この《バヤゼート》は、ハイムが手本とした1711年のピオヴェーネの《タメルラーノ》の台本に、イッポリート・ザネッラが大幅に手を加えたものでした。
この新しい台本は、オリジナルに比べずっとドラマティックな効果に優れていました。とりわけヘンデルを惹き付けたのが、幕切れ前の長大なバヤゼートの自害の場面でした。オリジナルの台本ではバヤゼートは舞台裏で死に、その知らせがタメルラーノたちに伝えられるだけだったのですが、新しい台本では舞台上でバヤゼートが壮絶な死(舞台裏へ引くとはいえ)を迎えるのです。ヘンデルがその斬新で強いインパクトのある場面に驚き喜んだのは容易に想像できます。
新しい台本にすっかり夢中になったヘンデルは、すぐさまハイムの台本を手直しし、新しい音楽を加え、さらに既に書き上げていた音楽も多く書き直しています。冒頭の捕われバヤゼートが引出される場面は最終稿に至るまで4回楽譜が作られ、最終稿は当初のものとはまるで違う、暗く力強い、オペラ全体を予感させる見事な音楽になっています。
ボロジーニは、テノールとはいっても、かなり独特なタイプだったようです。《タメルラーノ》では最高音は二点Aまで、それも限定的に用いています。ヘンデルは実際にボロジーニを聞く前に書いた音楽のうち高い音域の部分のいくつかを下げて書き直しています。おそらくは今でいうドラマティック・テノールないしは高いバリトンのような声だったのではないでしょうか。
ヘンデルはさらに初日の後に、バヤゼートの死の場面の効果を損なわないために、それに続くアステーリアの嘆きのアリアと、タメルラーノとアンドローニコが和解する二重唱(カストラートの二重唱!)をも取り除いてしまっています。
タメルラーノとは、歴史に名高いティムール帝国の創始者であるティムール(1336-1405) のヨーロッパでの通称(蔑称)です。
ティムールはサマルカンド近郊のケシュに生まれました(異説あり)。彼の祖先はチャガタイ=ハン国の名家だったようです。しかし移民のモンゴル系の民族は、100年以上にわたる多数のトルコ系民族との混血によって彼の世代には既にかなりトルコ人化しており、彼自身もイスラム教徒でしたから、単純に想像できるようなモンゴル人ではありません。ただ彼がチンギス=ハーンに強く憬れ、その再来を目指していたことは間違いないでしょう。
ティムールは若くして武勇を馳せ、1370年に西チャガタイ=ハン国の実質の支配者となり(形だけのハーンを置いて実権を握ったのです)、サルカマンドに都を置きました。これからティムール帝国の躍進が始まり、遠征に次ぐ遠征。その結果、1404年までに、中国の西方からインド北方を経てトルコにまで至る大帝国を築き上げることに成功しました。しかしこれに飽き足らないティムールは、元を滅ぼした明を征服するため東に向って大軍を進めますが、その途中猛烈な寒波にあい、老齢で寒さに耐えられず体調を崩し、1405年2月に亡くなりました。
ティムールの遠征の中でもおそらく最も有名なものが、オスマン帝国とのアンゴラの戦いです。
トルコを中心としたオスマン帝国は1299年に成立したばかりの新興国家で、第3代皇帝のムラト1世(在位1359-89)の時代に著しく発展しました。そしてその子第4代皇帝バヤジット1世(在位1389-1402)の時代にも拡大を続けていました。そして突如ティムールの侵攻を受けたのです。1402年7月、ティムール率いる大軍がアンカラ近郊でバヤジット1世率いるオスマン帝国軍(こちらも数万の大軍)が激突。夏場の厳しい暑さの中、優秀な騎兵からなるティムール軍がじりじりとオスマン帝国軍を追い詰め、夕刻までにはオスマン帝国軍は総崩れ状態になりました。バヤジット1世は退却中に捕らえられ、ティムールのもとに引っ立てられました。ティムールは彼を捕虜として扱わず、寛大に迎えたともいわれますが、いずれにせよ帝国を失ったバヤジット1世は失意の中1402年に病死します。
ちなみにオスマン帝国は、アンカラの戦いから50年後、名高いスルタン、メフメト2世(ロッシーニのオペラのマオメット2世)の時代に一気に大帝国に復活、なんと20世紀までの長命を保ちます。
このオペラはこうした背景をもとに、タメルラーノがトルコ王バヤゼーテの娘アステリアを我が物にしようとする話です。
タターリの皇帝タメルラーノはトルコを打ち破り、スルタンのバヤゼートを捕らえました。タメルラーノはトラビゾンダの王女イレーネと婚約をしていましたが、しかし彼はバヤゼートの娘アステーリアに恋をし、彼女を后にしようとするのです。アステーリアは、ギリシャの王子で今はタメルラーノに同盟(事実上の服従)をしているアンドローニコと相愛の仲です。
物語は全てトルコのブルサ Brusa(イスタンブールの南方に位置する町。イタリア語でプルーサ Prusa)のタメルラーノの宮殿の中で行なわれます。
第1幕
タメルラーノの命により、アンドローニコがバヤゼートの枷を外します。しかしバヤゼートはタメルラーノからのいかなる恩恵も受けないと、死を望みます。アンドローニコがアステーリアを思い出させるので、バヤゼートは娘への思いから死を思い留めます。タメルラーノが現れ、アステーリアを愛していることをアンドローニコに打ち明けます。驚くアンドローニコ。バヤゼートが同意すれば彼に自由を与え、そしてアンドローニコには褒美としてタメルラーノの婚約者でまもなく宮殿に到着するイレーネを与えるというのです。アンドローニコは驚きます。タメルラーノはアステーリアを呼び出し、彼女を自分の妻にすることと、アンドローニコの玉座を回復し、そしてイレーネと結婚させることにしたと告げます。玉座のために見捨てられたと思いこんだアステーリアは悲しみます。アンドローニコから話を聞いたバヤゼートは激怒しアステーリアに拒否の返事をするように言いますが、誤解をしているアステーリアが返答をしないので、バヤゼートが自分で断りに行きます。アンドローニコは頑ななアステーリアに悩みます。アステーリアも、愛する人の“裏切り”に心を引き裂かれます。イレーネが到着します。しかしアンドローニコから彼が彼女の花婿になったことを聞かされ、タメルラーノの心がわりに立腹します。しかしアンドローニコは、タメルラーノがまだ彼女の顔を知らないことを利用し、イレーネを彼女の侍女に変装させタメルラーノに近づかせることにします。一人残ったアンドローニコは、
辛い運命を嘆きながらも、彼女への変らぬ愛を誓います。
第2幕
タメルラーノはアステーリアが申し出を受けたとアンドローニコに告げ、自分の婚礼だけでなく、アンドローニコの婚礼も準備するよう命じます。アンドローニコとアステーリアが出会い、激しく言い争います。彼女の当てこすりにたまらずアンドローニコはタメルラーノと戦うと言いますが、彼女は既に時遅しと彼を突き放します。激しく絶望するアンドローニコ。彼はバヤゼートに助けを求めることにします。タメルラーノとアステーリアの前に変装したイレーネが現れます。タメルラーノは彼女の申し出を拒否し、アステーリアが自分を嫌ったらイレーネと結婚しようと言います。アステーリアはイレーネに、自分はタメルラーノを愛してはいないことを告白します。イレーネは再び希望を持ち始めます。一方、バヤゼートはアンドローニコからアステーリアが玉座に上ることを聞かされ憤激しています。バヤゼートはなんとしてでも阻止することにします。タメルラーノはアステーリアを玉座へ導きます。そこへバヤゼートが駈けつけ、タメルラーノの出身を激しく非難します。怒ったタメルラーノはバヤゼートに玉座の最下段に平伏すように命じます。するとバヤゼートは、玉座の前をふさぐように平伏します。アステーリアは玉座に上ることを拒否します。イレーネが呼ばれます(彼女はまだ変装したままです)。彼女は改めて玉座が明け渡されなければイレーネは現れないと告げます。タメルラーノに断わられ窮した彼女をバヤゼートが助け、アステーリアにタメルラーノを拒絶するように激しく訴えます。しかし反応がないので彼は他で死のうと出ていこうとします。アステーリアはついに、本当は玉座でタメルラーノを剣で殺そうと思っていたことを白状します。それを知ったタメルラーノは激しく怒り復讐を叫びます。三人はアステーリアの行動を称えます。
第3幕
アステーリアとバヤゼートは捕らえられています。バヤゼートはアステーリア、もしもの時のために毒薬を渡し、二人は名誉を守るために死を覚悟します。一方アンドローニコは意を決してタメルラーノに、自分がアステーリアの恋人だと宣言します。アステーリアも彼に応えるので、タメルラーノが完全に怒ってしまいます。彼がバヤゼートを殺すというと、アステーリアはひざまづいて慈悲を請います。そこへバヤゼートが現れるので、タメルラーノは三人を罰すると言い残し立ち去ります。死を覚悟して、アステーリアとアンドローニコは愛を確かめあいます。一方アステーリアの真意を知ったイレーネは、タメルラーノが自分の元に戻るなら受け入れようと思います。タメルラーノは食卓でアステーリアに王冠を断った罰として、奴隷として跪いて杯を差し出させることにします。アステーリアは密かに毒薬をその中へ入れますが、それをイレーネに見られてしまいます。タメルラーノが飲もうとする瞬間にイレーネが止めに入り、自分の正体を明かします。タメルラーノはバヤゼートかアンドローニコに飲ませるよう毒見させるようにとアステーリアに命ずる。アステーリアは自から飲もうとしますが、アンドローニコに杯を奪われます。タメルラーノは二度殺されかけて、アステーリアを殺すのではなく、ハーレムに行かせ辱めることにします。バヤゼートは死んでも蘇って復讐すると誓います。タメルラーノはイレーネと仲直りをします。そこへ、バヤゼートが勝ち誇った様子でやって来ます。彼は毒をあおり、もはやタメルラーノに殺されることはないと告げ、復讐の神を呼び求めます。涙に暮れるアステーリアを慰め、彼女に支えられて去っていきます。このあまりの自体にタメルラーノも心を動かされ、イレーネと結婚し、アステーリアをアンドローニコのもとに戻すことにします。父娘以外の一同の喜びで幕となります。
最終的な《タメルラーノ》の音楽の構成は次のようになっています。Bärenreiter社のUrtextを基にしています。
《タメルラーノ》の音楽設計一覧図
タイトルこそ《タメルラーノ》ですが、この役は第2カストラートのアンドレア・パチーニに与えられており、真の主役ではありません。第1カストラートの高名なセネジーノはアンドローニコ役ですが、この役は二枚目役とは言え、やはり主役とは言い難いもの。それだけバヤゼート役のボロジーニが引き立つように作られているのです。カストラート全盛の時代に、大スターを差し置いてまだ認知の低い声種が主役を張るというのは、大変珍しいことだったはずです(新聞にわざわざ「歌手になるための切断を受けていない」という記事がのったほど)。
バヤゼートの音楽は全て優れたものといって良いでしょう。とりわけ自害の場面は素晴らしい傑作です。この部分、レチタティーヴォ・セッコから始まり、激しいアッコンパニャート、レチタティーヴォ、極めて感動的なアリオーゾ"Figila mia, non pianger"、そしてアッコンパニャートがフリオーゾからラルゴへとかわり、静かに終ります。この10分近くもかかる大きな場面は極めてドラマティックで、バロックオペラとしては異例の劇的場面です。
自害の場面の前の35番のアリアはEmpio, per farti guerraも、バヤゼートの強い怒りが表現されています。ボロジーニの力強さはここで最高に発揮されています。19番のA suoi piediの死をかけて娘を引き戻そうとする父の苦悩も見事。
そしてなにより冒頭のアリア、Forte e lieto a morte andreiの気高い嘆き!先に述べたようにこの冒頭の場面はヘンデルが何度も書き直しをしており、このアリアもようやく到達した音楽なのです。悲しみのこもった父の娘への愛情が見事に音楽になっています。
アンドローニコの曲は、セネジーノの魅力を引出した美感に満ちたものばかり。5番のBella Asteriaはニ長調、ラルゴの幅広い伸びやかさが素晴らしいものです。12番のBenche mi sprezzi、16番のCerco in vanoはいずれもレチタティーヴォ・アッコンパニャートを伴い、アンドローニコの苦悩の滲んだ渋い美しさが映えています。ただ、全体としてアンドローニコの弱腰の印象ばかりで、熱っぽいものはありません。
タメルラーノは重要な役のわりには大帝国の皇帝の威厳や征服者の残忍さがなく、それはそのまま音楽の特徴にもなっています。4番のVuò dar pace a un'alma alteraはコミカルで間抜けな印象さえありますし、13番のBella garaは付点を多く用いて軽薄さが出ています。第3幕、ついに怒り心頭になって歌う28番のA dispettoでカストラートらしい装飾のたっぷりついた火の出るようなアリアになっています。
面白いのは、初演直後に破棄されてしまったと思われる幕切れ直前のアンドローニコとタメルラーノの二重唱Coronata di giglie e di rose。このヘンデルには珍しいカストラートの二重唱では二人の和解が歌われるのですが、バヤゼートの壮絶な死の後ではあまりにも明るく、効果的でないと削除されてしまったのは仕方ないでしょう。しかし単独で聞くなら非常に美しい曲です。
アステーリアは一貫して悲しみに満ちた曲です。とりわけ9番のDeh, lasciatemiのしっとりしたアリアが素晴らしいもの。またアンドローニコとの二重唱Vivo in teの切なさも素晴らしいものです。また、アステーリアの音楽で忘れてはならないのは、最終的にカットされてしまった最後のアリアPadre amatoです。嬰へ短調という珍しい調性で書かれた、ラメントな色彩が美しいものです。
イレーネのアリアでは、10番のDal crudel che m'ha traditaの烈火のごときコロラトゥーラがヘンデルの本領発揮でしょう。
ほとんど活躍しない脇役のレオーネに、大変立派な追加アリアがあります。1731年の再演の際に加えられたNel mondo e nell'abissoで、脇役にはもったいないくらいの堂々とした立派なものです。
幕切れのコーロが面白いもので、自害したバヤゼートと彼を追って出て行ったアステーリアは参加せず、4人だけで歌われます。そして調性はなんとホ短調。何か重苦さの抜け切れない大団円となっています。
初演時の歌手は、次のような大変豪華なものでした。
| Tamerlano | Andrea Pacini | Alto castrato |
| Bajazet | Francesco Borosini | Tenore |
| Asteria | Francesca Cuzzoni | Soprano |
| Andronico | Francesco Bernaldi (Senesino) | Alto castrato |
| Irene | Anna Dotti | Contralto |
| Leone | Giuseppe Boschi | Basso |
《タメルラーノ》は、初演前に改訂が込んだ上に、1731年の再演で追加、削除された部分もあるため、今日上演される際には楽譜の選択はかなりまちまちとなっています。
参考まで、現在聞くことができる主な上演形態の《タメルラーノ》使用楽譜の比較一覧表を作成してみました。
この時代のオペラからは創造できないドラマティックな激しさを持ったヘンデル絶頂期の傑作です。これは聞き逃せないでしょう!
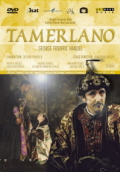
Bacelli, Randle, Pushee, Bnitatibus, Norberg-Schulz, Abete
The English Concert
Pinnock
Halle, June 2001
Arthous Musik 100 703 (DVD)
2001年の第50回ハレ・ヘンデル音楽祭でのライヴ収録の映像。DVDにはどこにも細かい日付がないのですが、音楽祭は6月に催されます。会場はハレ近郊のバート・ラウフシュテットにあるゲーテ劇場。1802年開場の由緒ある劇場で、450人収容と非常に小ぶりで、ステージもピットもかなり小さいものです。ただし古典派の時代の劇場なので、機械仕掛などの装置は全くなく、バロックオペラを上演するに向いているとはあまり言えません。
なにより日本語字幕が選択できるDVDであることがありがたく、対訳がない現状では最もとっかかりがよいでしょう。
ジョナサン・ミラーの演出は、舞台上での動きやセットにはほとんど工夫がなく、その分衣装(ジュディ・レヴィン)の豪華さを強調しています。しかしいかんせん動きが乏しいため限界があり、第3幕などもっと迫真の舞台が作れたと思うのですが、冗長気味なのは不満です。なお、19番のバヤゼートのアリアまで通しており、全体を2幕仕立てにしています。
とにかくバヤゼート役のトーマス・ランドルの力強い歌と演技に圧倒されます。ヘンデルにしてはかなり太い声なのですが、真摯に役に没入しており、存在感は大です。タメルラーノ役のバチェッリは、声も女性的ですし、細身の身体が災いして、アステーリアを狙う男としての存在がやや希薄です。ノルベリ・シュルツはどうも表情も動きも単調で、アステーリアの苦悩が伝わらないのはマイナスでしょう。アンナ・ボニタティブスのビシッとしたイレーネが気持ち良いもの。
驚くほどたくさんの特典映像付き。
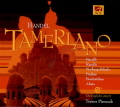
Bacelli, Randle, Pushee, Bnitatibus, Norberg-Schulz, Abete
The English Concert
Pinnock
London, 27, 28 & 30 June 2001
Avie AV 0001
こちらはロンドンのサドラーズ・ウェルズ劇場でのライブ収録。バート・ラウフシュテットでの上演の直後です。
異なる上演とはいえ、キャストは全く同一、演奏の印象もほとんど同じです。音の収録の状態もそれほど変わりません。値段も多少の差くらい。DVDの機械があるなら、日本語字幕のあるDVDの方がずっと便利でしょう。
音だけでもやはりランドルが圧倒的です。
ピノックの指揮は全体に優秀に丁寧にまとめているのですが、終始穏便でリズムが平板なため、ヘンデルが《タメルラーノ》に込めた激しいドラマが伝わりきらない不満が残ります。バヤゼートの死の場面(特にフリオーゾの部分)もランドルの熱演のわりにはオーケストラが盛りあがらなかったり、10番でボニタティブスの方がオーケストラを煽るといった感じです。
楽譜の選択は、多少カットがある以外は一般的です。ただし2幕仕立にするため、本来の第2幕の幕切の26番をカットし、27番を破棄されたバヤゼートのアリアに差替えています。また基本的に1731年の再演の際のレチタティーヴォ・セッコのカットを採用しています。詳しくは《タメルラーノ》使用楽譜の比較一覧表を御覧下さい。
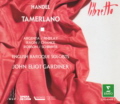
Ragin,Robson,Argenta,Chance,Findlay,Schirrer
English Baroque Soloists
Gardiner
Koln,17-18 June 1985
ERAT 2292-45408-2
ナイジェル・ロブソンの英語の訛のイタリア語がかなり気になります。タメルラーノをカウンターテナーのデレク・リー・レギンが受け持っており、これは悪くないでしょう。
ガーディナーの指揮は、スタジオの中で理性が勝り過ぎた感じです。それでも彼ならではの鋭い視点の音楽づくりが生きている場面はあちこちあります。ただ今だったらもっとオペラティックな興奮を作れるでしょう。
第2幕の最後のアリアを当初の予定通り27番のアステーリアのアリアにし、第3幕の冒頭には破棄されたバヤゼートのアリアを採用しています。このSù la sponda del pigro leteも大変に感動的なアリアです。また幕切れ前のアリアと二重唱を完全に復活させています。
これも基本的に1731年の再演の際のレチタティーヴォ・セッコのカットを採用していますが、若干独自の判断をしています。詳しくは《タメルラーノ》使用楽譜の比較一覧表を御覧下さい。
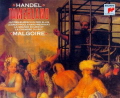
Ledroit,Elwes,van der Sluis,Jacobs,Poulenard,Reinhart
La Grande Ecurie et la Chambre du Roy
Malgoire
Paris,13-20 February 1983
SONY CLASSICAL SM3K 37 893
タメルラーノのアンリ・ルドロワが独特の味があって個性的です。復活したアンドローニコとタメルラーノの二重唱はこちらの方が美しいでしょう。バヤゼートを歌うジョン・エルウィズは声も表現も良いのですが、二点Aあたりで突っ張るのが気になります。
マルゴワール独特のゆっくりとしたテンポのもったりした音楽で、スピード感のあるスリルには欠けるものの、リズムの立ちや呼吸感は豊かなので、この流儀に慣れれば楽しめます。
非常に独特な楽譜の選択をしています。第1幕は、1731年のカットも採用せずほぼちゃんと収録されているのですが、どういう訳か第2幕が大幅に刈り込まれています。第3幕には珍しくイレーネとタメルラーノの二重唱が挿入されている他、幕切れ前のアリア(ただしアッコンパニャートの部分のみ)と二重唱が復活しています。またイレーネの二つのアリアは珍しくソプラノの稿を用いています。詳しくは《タメルラーノ》使用楽譜の比較一覧表を御覧下さい。