RODELINDA, Regina de'Lomgobardi
HWV19
オペラ イタリア語
初演:1725年2月13日、ロンドン、ヘイマーケット国王劇場
台本:フランチェスコ・ニコラ・ハイム
原作:ピエール・コルネイユの悲劇「ペルタリト」(1652)
→アントーニオ・サルヴィのオペラ台本「ロデリンダ」(作曲はジャコモ・アントーニオ・ペルティ、1710)
「ジューリオ・チェーザレ」、「タメルラーノ」と傑作を立続けに作曲、波に乗るヘンデルが次に手掛けたのが、ヘンデルのオペラの中でもとりわけ完成度の高さでは屈指の名作「ロデリンダ」です。
この物語の背景にあるロンバルド(ランゴバルド)王国の歴史は、日本人にはよくわからないものでしょうから、ごく簡単に説明しておきましょう。
4世紀にフン族の西進をきっかけとしてゲルマン民族の移動が始まります。6世紀の後半に入って、ライン東岸に居住していたロンバルド族が北イタリアに入り、568年に王国を作ります。この王国は、教皇ハドリアヌス1世の要請でカール大帝が774年に滅ぼすまで続きます。
8代目の国王、アリペルト1世(在位653-661)は王国を二人の息子に分割して相続させます。ヴェネベントの公爵グリモアルドはパヴィアを受け継いだゴデベルトを助けに行きながら彼を殺し、ミラノに居た兄のペルクタリトは逃亡します。グリムヴァルトの死後ガリバルドが国王になり、さらにその後、ペルクタリトが復帰し国王となります。
この史実をもとに、当然様々なフィクションを盛り込んでいます。
7世紀のロンゴバルト。国王アリベルトの死後、王国は兄弟に分割され、ベルタリードがミラノを、グンデベルトはパヴィアを治めます。グンデベルトは妹エドウイージェを愛するグリモアルドとともにミラノを攻め、逃亡したベルタリードは遥かフン王国(ハンガリー)で亡くなったとの情報が入ります。そしてグンデベルトの死後、グリモアルドが国王になります。ここまでが物語の前程です。
ミラノの王宮。ロデリンダはベルタリドの死を嘆き悲しんでいます。グリモアルドは彼女との結婚を求めていますが、ロデリンダは撥ね付けます。エドゥイージェが現われ、王になってから愛を失ったグリモアルドの態度を非難しますが、かえってかつてグリモアルドの求愛を撥ね付けたことに嫌みを言われてしまいます。怒ったエドゥイ―ジェは自分を愛しているガリバルドに復讐を誓わせます。ところがガリバルドも単に権力欲しさにエドゥイージェに近づいているだけです。歴代の国王が眠る墓地。フン族の衣装をしたベルタリードが真新しい自分の墓を見つけ嘆きます。腹心のウヌルフォが彼を見つけ再会を喜んでいると、そこへロデリンダが息子を連れて墓にやってきます。ひとまずウヌルフォはベルタリードを物陰に隠します。さらにガリバルドがやって来て、グリモアルドとの結婚を受け入れないなら息子の命はないと脅します。やむ無く受け入れると返事をするロデリンダに、隠れて様子を見ていたベルタリードはショックを受け、しばらくは姿を表さずに自体を見て行くことにします。王宮ではエドゥイージェがロデリンダにグリモアルドへの怒りを爆発させています。そのグリモアルドは、ロデリンダが本当に求婚を受け入れたかと尋ねます。ロデリンダはしかし妻にしたいならまず息子を殺しなさい、と激しくつめより、弱腰のグリモアルドは恐れをなします。ガリバルドは冷ややかに事態を見、ウヌルフォに自分の野心を語ります。庭園でエドゥイージェは兄ベルタリードに出会います。ウヌルフォがロデリンダの貞節な行動を伝え、ベルタリードは喜びます。王宮でロデリンダは夫と再会。そこにグリモアルドが現れ、変装しているベルタリードと抱き合うロデリンダを非難し、ベルタリードの逮捕を命じます。二人は別れる前につかの間愛を語り合います。エドゥイジェはウヌルフォに地下牢の秘密の通路を開ける鍵をウヌルフォに渡します。一方グリモアルドは、ガリバルドの野心にもはやついていけず動揺しています。牢獄のベルタリードのもとにエドゥイージェが投げこんだ剣が落ちます。誰かが牢にやってくるので、ベルタリードが斬りつけるとそれはウヌルフォ。ウヌルフォは怪我をしますが、ベルタリドを着替えさせ牢から脱出します。その後に牢にやって来たロデリンダは、血と服からベルタリードが殺されたものと思い悲しみます。庭園。グリモアルドは悩み疲れ眠りに落ちてしまいます。ガリバルドは王位簒奪のチャンスとばかりグリモアルドの剣を奪い切りかかろうとしますが、ベルタリードに追い払われてしまいます。ガリバルドを殺し剣をグリモアルドに返し、ベルタリドは、暴君よその剣で自分も殺せ、と訴えます。自分の命を助けたのがベルタリードだと知りグリモアルドは驚き、ロデリンダ達の前で王権とロデリンダをベルタリードに返すと告げます。全員の喜びで幕となります。
バロックオペラでは珍しいほど物語の展開に無駄がありません。ハイムの台本のもととなったサルヴィの台本が、コルネイユの原作をオペラ向きに巧みに翻案していることと、ハイムがそれをさらにコンパクトにまとめた(イタリア語の理解できないロンドンの聴衆に長いレチタティーヴォを我慢してもらうことは期待できませんから)ことで、効果的な台本となったのでしょう。
音楽に関してはそのほとんどが傑作といって良いほど充実したものぞろいです。
タイトルロールのロデリンダに与えられれたアリアはどれも見事なものです。開幕早々、夫が亡くなったと聞かされ嘆く"Hò perduto il caro sposo"は、舞台を一気に悲劇的な雰囲気に持って行きます。その他、ロデリンダのアリアは、悲しみ(第1幕の"Ombre, piante, urne funeste!"、第3幕の"Se'l mio duol non è si forte")や喜び(第2幕でベルタリードが生きていると知って喜ぶ"Ritorna, oh caro e dolce mio tesoro"、第3幕の"Mio caro bene!")、さらに怒り(第1幕の"L'empio rigor del fato vile non potrà"と"Morrai sì, l'empia tua testa"、第2幕の"Spietati, io vi giurai")といった感情が幅広く表現できるようになっており、プリマドンナの魅力が存分に発揮できるようになっています。
ベルタリードは、まず登場の場面が大変感動的です。自分の墓を見つけて嘆くレチタティーヴォ・アッコンパニャートの"Pompe vane di morte!"、それに続くロデリンダを思って歌う"Dove sei? Amato bene!"の静かな、しかし熱い感情の表現はヘンデルの充実した筆が存分に現れています。そしてベルタリードのアリアでは、何と言っても大詰めの"Vivi, tiranno!"が実にカッコいい!数あるヘンデルの男声のアリアの中でも最もヒロイックなものでしょう。このアリアは再演1725年12月8日からの再演の際に追加されたものですが、今では「ロデリンダ」には欠かせない曲になっています。
そしてこの二人のニ重唱、第2幕の幕切れの"Io t'abbraccio"の実に切ないこと!当時の多くの御婦人がここで涙したことでしょう。
悪役の二人、グリモアルド(テノール)とガリバルド(バス)には対照的な曲が与えられています。
弱気なグリモアルドのアリアは、全体としてはあまり個性的でないのですが、ところが第3幕で困惑して歌う"Trà: sospetti, affetti, e timori"は半音階的な動きを多用した、足元がぐらつくような非常に強烈なものです。
一方、策謀者ガリバルドにはわずか2曲しかアリアがありません。しかし第1幕の"Di Cupido impiego i vanni"はいかにも悪役といった押しの強さがあります。
エドゥイージェがグリモアルドに怒る"Lo farò, diròspietato"は見事なメッゾの怒りのアリアですし、
「ロデリンダ」は初演当時から大変好評で、初演時には14回の公演がありました。フランチェスカ・クッツォーニのロデリンダ、セネジーノ(フランチェスコ・ベルナルディ)のベルタリード、フランチェスコ・ボロジーニのグリモアルド、ジュゼッペ・マリア・ボスキのガリバルドと、歌手もこの上なく強力。 同じ年の12月から翌年にかけてほぼ同じメンバーで8回(この時"Vivi, tiranno!"など4曲が追加、差替えされています)再演、さらに1731年に8回再演されるなど、人気の高い作品でした。
引き締まった台本ということで、「ロデリンダ」は「ジューリオ・チェーザレ」や「セルセ」についで今世紀での復活は早く、また戦前からしばしば上演されていました。
ヘンデル全盛期の傑作ですから、これはぜひとも聞いていただきたい作品です。

Labell, Blaze, Paton, Wolak, van de Sant, Foster
Concerto Köln
McGegan
Göttingen, June 2000
Göttingner Händel-Gesellschaft
ゲッティンゲンのヘンデル・フェスティヴァルでの上演のライブ録音で、音楽祭の自主製作盤。会員のみの限定配布です。
ヘンデルのスペシャリスト、マッギガンの指揮は序曲から気迫十分、かつての真面目なばかりの音楽からずっと円熟しており、文句なしです。ライブの熱気もたっぷりで興奮できます。
歌手ではブレイズのベルタリードが高水準で、"Vivi, tiranno!"の後で聴衆が熱狂しています。ラベルは悪くないものの、後半調子が悪そうです。エドゥイージェのウォラクも存在感があります。
第1幕のグリモアルドの"Se per te giungo a godere"(と先立つレチタティーヴォ)はカット。また、第1幕のロデリンダの"Hò perduto"、第2幕のベルタリードの"Scaccia dal suo nido sen vola"、グリモアルドの"Tuo drudo è mio rivale"は、いずれもダ・カーポ・アリアのAの部分のみ。

Daneman,Taylor,Thompson,Robbin,Blaze,Purves
Raglan Baroque Players
Kraemer
London,13-17 February 1996
VERGIN VERITAS
クレーマーの指揮は丁寧で、音色もきれいです。ただ全体におっとりしすぎていて、あまり熱気のあるものではありません。
歌手ではベルタリオのテイラーがなめらかな声で良いですが、迫力には欠けます。ロデリンダを歌うデインマンは悪くないのですが、ただ時々妙に声がハスキーになるのはどうしたことでしょう。ウヌルフォを歌うカウンターテノールがメチャメチャうまい!と思ったら、ブレイズでした。
これも第1幕のグリモアルドの"Se per te giungo a godere"とその前のレチタティーヴォはカット。さらにベルタリードの"Scaccia dal suo nido sen vola"もカット。
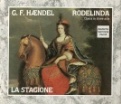
Schlick,Cordier,Pregardien,Schubert,Wessel,Schwartz
La Stagione Frankfurt
Schneider
Frankfurt,3-4 June 1990
DEUTSCHE HARMONIA MUNDI RD77192
シュナイダーの音楽はやたら鋭角的で、あまり心地よいものではありません。男声低音は充実していますが、ベルタリードを歌うコーディエーにはかなり不満が残ります。
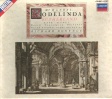
Sutherland,Nafe,Rayam,Buchanan,Tourangeau,Ramey
Welsh National Opera Orchestra
Bonynge
London,April & May 1985
LONDON(DECCA) F70L-50449/50 (414 667-2)
サザランドはロデリンダ役を得意とし度々歌っていますが、しかしこの録音は彼女にとってあまりにも遅すぎました!ボニングの指揮も厚ぼったすぎます。レイミーの見事なガリバルドが救い。
カット多数。
ヘンデル御殿のホームページに戻る
オペラ御殿 メインメニューに戻る
|